どうも!Naoyukiです!
今回は周手術期の実習について取り上げようと思うのですが
周手術期の実習といえば
実習の山場周手術期実習も今日入れてあと4日………あと、4日………(‘、3_ヽ)_
— 橘祐樹@虎廃 (@tachibana_wa3) June 30, 2016
明日から周手術実習!3年になって初めての一般病棟(^O^)不安だらけだけど頑張るしかない(*´▽`*)∩
— natsumi (@1655Okd0820) June 12, 2013
とこのように「大変だ」、「ツライ」、「不安」などネガティブなイメージが多い実習ですし、これから周手術期の実習にいく看護学生もそのようなイメージを抱いているのではないかなーと思います。
そこで、今回はどうして周手術期の実習が大変だと言われているのかを解説するとともに、周手術期の実習に向けての効果的な事前学習の方法も解説していこうと思います。
今回の記事を読むとわかること
・周手術期の実習が大変な理由
・周手術期の実習に向けた効果的な事前学習の方法
周手術期の実習はどうしてツライのか?
周手術期の実習がツライ理由のほとんどが「実習記録」に関することです。
実際に周手術期の実習を経験した人のツイートを見てみると
それね?!!!実習記録とかもうキツすぎて吐きそう…特に周手術期とかやばいよね…。
あーーなるほどね😖
皮膚科とか眼科とか、デイサービスなら命云々はあんまりないだろうし、いいかもね🥰— 水咲 杏樹 (@anju_hobby) August 12, 2019
周手術の実習のときどんだけ頑張って記録を書いても3時間睡眠になってたしちょうど10週間実習の真っ只中だから、もう完全に頭のどこかはイカれてたと思うし睡眠の素晴らしさを知った。
— 麦飯⭐️スタライ 12/14.15 (@RMmugi15) October 14, 2016
周手術期の実習記録に関する悩みをつぶやいていますよね!
でも、ここで少し考えたいのが
「どうして周手術期の実習記録は大変なのか?」ということです。
実習記録は看護学生の最大の敵といっても過言ではない。
周手術期に関わらず、慢性期の実習や小児、在宅実習でも実習記録は厄介なのは変わらないハズ…。
それでは、どうして周手術期の実習記録が大変になるのか解説します。
周手術期の実習記録が大変になりやすい理由その①
「受け持つ患者が多い」
手術部位や術式によりますが入院期間の短縮に伴い、1週間から10日間程で退院することが多いです。その為、2週間から3週間の実習期間中に2人ないし3人の患者を受け持つと思います。
実習記録も受け持った患者さん人数分、展開することになるので、大変になりますね。
周手術期の実習記録が大変になりやすい理由その②
「看護展開をタイトなスケジュールで行わないといけない」
理由その①でも、1週間〜10日間で退院することが多いと話しました。
ということは
情報収集→アセスメント→看護問題の抽出→看護計画の立案→看護計画の実践と修正、評価
このプロセスをわずか、1週間ないし10日間でやらないといけないわけです。
周手術期の実習記録が大変になりやすい理由その③
「看護問題が多い」
周手術期の実習における看護問題は主に術後合併症に関する問題になります。
術後合併症は後出血、無気肺、肺炎、イレウス、深部静脈血栓症、感染、疼痛など沢山ありますよね。
実習で受け持つ患者さんに全て当てはまることはないとは思いますが、それでも、4〜5つの看護問題が当てはまってくると思います。
抽出した看護問題はそのまま、看護計画の立案につながるので、看護計画の内容も沢山考えないといけなくなります。
以上の3つの理由が周手術期の実習記録が大変になる理由になりまります。
話をまとめると
・周手術期の実習がツライ理由は実習記録が大変だから
・実習記録が大変な理由としては
受け持つ患者が多い+看護問題が多い+タイトなスケジュールで看護展開しないといけない
それでは、周手術期の実習を少しでも楽にするにはどんな対策が必要か次の見出しで解説しようと思います。
周手術期の実習に向けた効果的な事前学習の方法とは?
秋手術期の実習に向けてどんな対策が必要になるかというと「事前学習」をきちんとすることになります。
事前学習と聞くと
「範囲が広くて何をしたら良いかわからない」
「勉強した疾患の患者を受け持たないなら意味ないんじゃないの?」
などの意見が出ると思います。
周手術期の事前学習に関しては、性別、疾患、術式が違っても、共通する内容があります。
それが、「術後合併症」に関する内容です。
全身麻酔による手術を受ける患者の場合は術式や手術部位に関わらず、全身麻酔と手術侵襲によって生じる術後合併症は共通してきます。
例を挙げると、後出血や呼吸器合併症、深部静脈血栓症などがあります。
周手術期の実習において教員または指導者から求められる視点(評価の視点)は
① 患者の既往歴、術前の検査結果、手術部位、麻酔の方法、術式などから起こりやすい術後合併症を予測しているか?
② ①で予測した術後合併症に関する看護計画の立案と合併症の発症予防のための看護実践ができていたか?
の二つがメインになります。
①については術後合併症が麻酔や手術侵襲によってどうして起こるのかを調べることによって、術前の状態から術後合併症を予測することが可能になります。
術後の呼吸器合併症である無気肺を例に挙げると
吸入麻酔薬→気管支の末梢が狭くなる→気道内分泌物が貯留しやすくなる→肺胞が膨らまない→無気肺
吸入麻酔による無気肺を引き起こす要因がこのようにありますよね。
もちろん、無気肺の要因は上記のプロセス以外にもあります。
この一つのプロセスに、喫煙歴が長い(ブリンクマン指数が高値)、喘息の有無や閉塞性換気障害がある(1秒率が低い)などの無気肺の発症に関わる要因が加わることで、術後のリスクが高いか低いかをアセスメントできるようになります。
そのためにも、術後の無気肺がどうして起きるのか、どんな既往歴や生活背景があると無気肺を発症しやすいのか、無気肺に関する採血データや呼吸機能検査と正常値を調べることが重要になってきます。
言い換えると、全身麻酔で手術を受ける患者さんは無気肺を発症するリスクはあるわけで、全身麻酔以外の要因がないかを情報収集していければ問題ないわけです。
② ①で予測した術後合併症の予防のための看護実践ができていたか?についてですが、先述した無気肺を予防するために必要な看護援助として代表的な物として、「深呼吸」がありますよね。
深呼吸を促すことによって肺胞を膨らませることができます。
他にも喀痰を促すことで気道内分泌物を除去し、肺胞の虚脱を防ぐことも可能ですよね。
喀痰を容易にするためにも、手術部位の疼痛を評価し、必要時は鎮痛剤を投与することが必要になります。
このように、無気肺を予防するためにどんな援助が事前に調べておくことが重要となります。
術後合併症を予防するために必要な援助は術後合併症の看護計画の援助項目(TーP)に直結してきます。
なので、術後合併症予防のための看護援助を考えることは、術後合併症の看護計画の援助項目(TーP)を考えることになる訳です。
援助の実践については、指導教員または指導者と一緒に安全に注意して実践していくので心配ないですよ。
いささか、話がふくらんじゃいましたね。
今までの話をまとめると
周手術期の実習に向けての効果的な事前学習の内容は「術後合併症」に関すること
学習の仕方については
・術後合併症の発症に関わる要因を調べること
・術後合併症を要望するために必要な看護援助を調べること
周手術期の事前学習をするときのヒントにしてくださいね!
まとめ
今回は周手術期の実習が辛くなる理由と効果的な事前学習の方法を一部紹介しました。
周手術期の実習は記録が大変ですが、事前学習をしっかりしておけば、記録の大変さを減らすことは可能です。
実習記録が大変だと、受け持たせてもらっている患者さんとも十分に向き合うのも難しくなります。
今回、解説していた内容が皆さんのお役に立てたら嬉しいです!!!
引き続き、周手術期の実習が楽になるための情報をお伝えしたいと思います!
今回も最後まで読んでいただきありがとうございます!
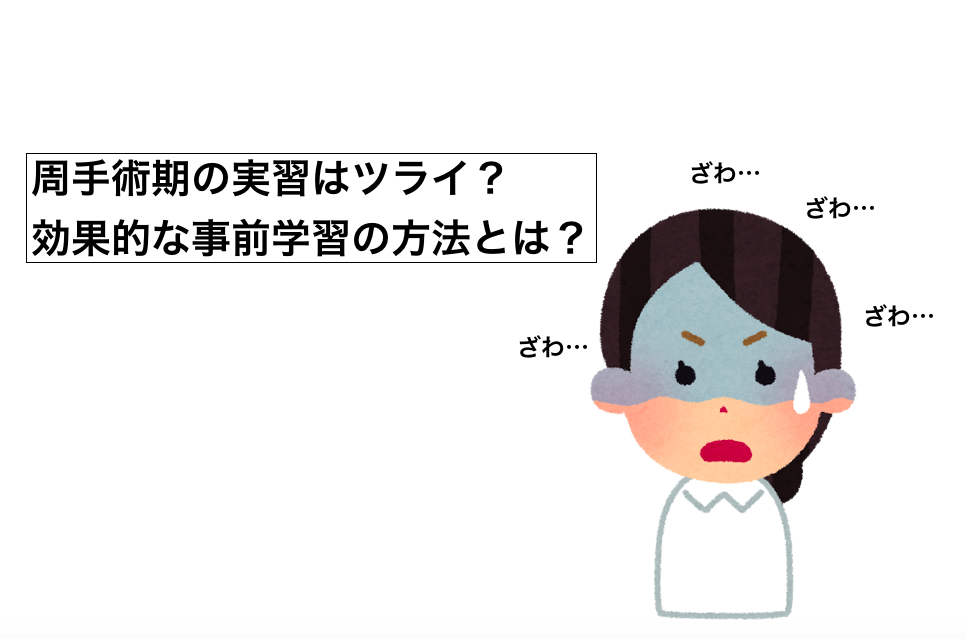
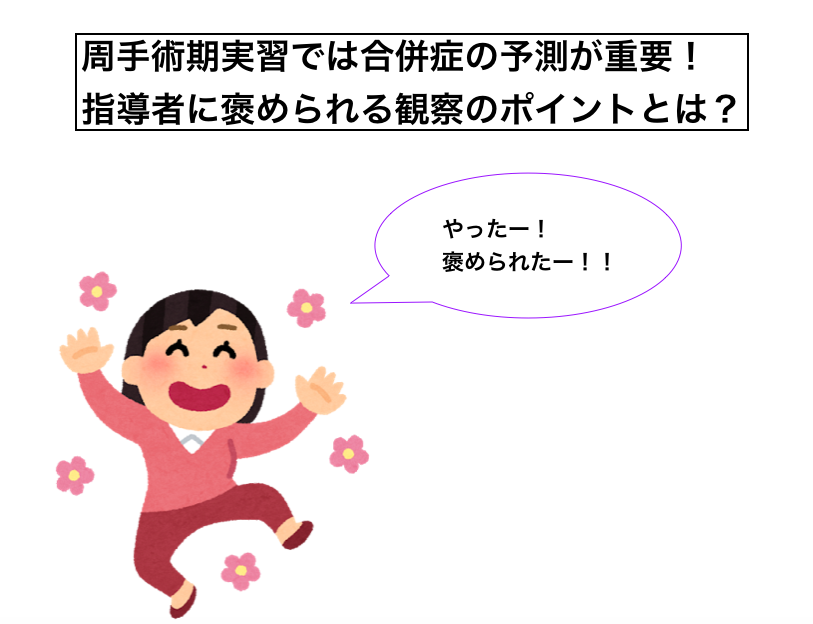
コメント